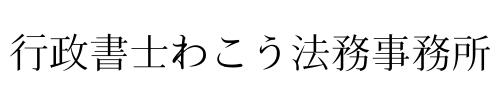後見制度について(概説)
①後見制度はどのような人が利用するか
後見制度は、判断能力が不十分な人を法的に支援する制度です。主に以下のような人が利用します。
- 認知症の高齢者:財産管理や契約などが難しくなった場合
- 知的障害のある人:日常的な金銭管理や法律行為の支援が必要な場合
- 精神障害のある人:病状によって適切な判断が難しい場合
本人の利益を守るため、家庭裁判所の監督のもとで後見人が選ばれ、財産管理や法律行為を支援します。
②後見の類型
後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見の2種類があります。
1. 法定後見制度(家庭裁判所が後見人を選任)
判断能力の程度に応じて、次の3つの類型に分かれます。
- 後見:判断能力がほぼない人(認知症が重度など)が対象。後見人がほぼすべての法律行為を代理。
- 保佐:判断能力が著しく不十分な人が対象。重要な契約は保佐人の同意が必要。
- 補助:判断能力が不十分な人が対象。特定の行為について補助人が同意や代理を行う。
2. 任意後見制度(本人が元気なうちに契約)
本人が判断能力を失う前に、将来の後見人を自ら選んで契約を結ぶ制度。必要になった時に家庭裁判所の監督のもとで後見人が活動開始。
③行政書士は後見人になることができます。
行政書士も後見人になることができます。法律上、後見人になれるのは家庭裁判所が適任と認めた者であり、行政書士資格がなくても後見人になれますが、行政書士は法律や書類作成の専門家であり、後見人として適任とされることが多いです。
特に、行政書士が後見人になる場合、以下のような業務が強みになります。
- 財産管理や契約手続きの代理
- 各種申請や役所への届出
- 遺言書や任意後見契約の作成支援
ただし、本人の財産を適切に管理し、不正を行わないことが求められるため、家庭裁判所の監督を受ける点には注意が必要です。行政書士のほか、弁護士や司法書士、親族も後見人になれます。
このように、後見制度は判断能力が不十分な人を支援するための仕組みであり、行政書士も後見人として活躍できる立場にあります。
お悩みの際はご相談ください。
行政書士わこう法務事務所
行政書士若生徹也
080-9611-9591